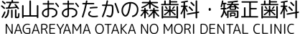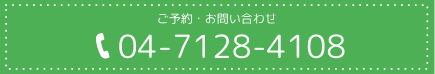小児歯科

お子さまの歯とお口の長期的な健康を考えるみなさまへ
当院は一般歯科医、矯正歯科医、歯科衛生士による連携体制をとっているため、お子さまの歯やお口のケアについて、予防や虫歯治療、歯並びなどをトータルで診ることが可能です。
お子さまの口内は、生まれてから数年で大きく環境が変化しますが、この間に歯が生えそろい、お口のケア習慣が確立されて、歯やお口の基礎が作られます。そのため、この小児期にどのようなケアを行っていたかが、お子さまの歯とお口の長期的な健康を左右します。
歯並びに関しては、継続して経過を診ることで、最適なタイミングで矯正治療のご提案をすることができます。 どんなトラブルも、できるだけ未然に防ぎ、症状が軽いうちに対処することで、体への負担を減らすことが可能です。お子さまの歯やお口の健康を守るのはもちろん、お子さまを苦痛・不快から守るためにも、早くからきちんとした口内ケアを行うことが大切です。
小児歯科は何歳から受診したらいいの?

「小児歯科は何歳から」という決まりはなく、年齢による制限はありません。早いお子さまは、乳歯が1~2本生えてきた頃から検診にいらっしゃいます。
幼いお子さまの検診の目的は、何より磨き残しに気付いてもらうことです。磨き残しは、いずれ歯ぐきの炎症による歯肉炎や虫歯に移行してしまいます。それを防ぐためには、磨き残しをなくしていくことが必要です。
当院では、検診の際に、磨き方の指導やアドバイスも行っています。
なお、お子さまの診療に関しては、市からの助成があるため、どのお子さまも200円〜300円で受診が可能です(市によって異なります)。
お子さまの歯やお口のケアにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
早いうちに小児歯科を受診するメリットは?
お子さまが早くから検診を受けるメリットは、大きく2つあります。
ひとつめは、早いうちから磨き残しをなくすことで、お子さまの歯やお口のトラブルを未然に防げるという点です。
乳歯が生え始める年齢で、泣かずに検診を受けられるお子さまは、まずいません。泣いているお子さまを見ると、ご両親は心が痛むかもしれませんが、もし磨き残しが積み重なって虫歯ができてしまうと、治療でつらい思いをするのはご両親ではなくお子さまです。そのため、なるべくお子さまがつらい体験をしなくて済むように、早くからきちんとした歯磨きをマスターしていただくことが大切です。

ふたつめは、歯医者への苦手意識を持つ前に、歯医者に慣れさせることができるという点です。
大人の方でも歯医者が苦手という方はたくさんいらっしゃいます。苦手なところは、誰でも行きたくありません。しかし、行きたくないからと言って、歯やお口のトラブルを放置してしまうと、後々取り返しのつかないことになることがあります。このようにならないためにも、最初から歯医者を苦手にさせないことが重要です。
子どもは、医科の方でワクチン注射などを経験しているので、同じような病院特有の雰囲気を感じ取って怖くなってしまい、泣き出してしまうケースが多くあります。
だからこそ、なんでもない時から歯医者に通うことで、「歯医者は歯磨きをしてお口を見るところで、痛いことをするところではないんだよ」ということをお子さまに知ってもらうことが必要になります。
なお、お子さまが歯医者に来院する理由は、実は「予防や虫歯治療」だけではありません。転倒して歯をぶつけたり、口の中を切ったりと外傷で来院することも多いのです。
そんな時、歯医者が初めてとなると、ただえさえ外傷で痛みを感じている中で、不安も感じやすいので、口の中を見させてもらい、状態を確認するだけでもかなり大変です。時間がかかるほど、お子さまの苦痛も大きくなってしまいます。
そのため、小さなお子さまについては、歯医者そのものに慣れるまで、多少短い周期での検診をご提案しています。
幼稚園や保育園に入園した後の検診はどうしたらいいの?
多くの幼稚園・保育園では、年に1回歯科検診があると思います。ただ、口の中に手を入れての検診ではないので、 はっきりとわかる大きな虫歯以外、歯の異常を見つけるのはなかなか困難です。
また、幼稚園や保育園に通い始めると、お子さまはより活動的になり、転んで口の中をケガしてしまうこともあります。
お口の中の環境の変化に早く気付き、対処していくためにも、できれば3~4ヶ月に1度は歯医者さんでしっかりとした検診を受けるのが安心です。

子どもの虫歯治療はどのように行うの?

子どもの虫歯治療の方法は、
- 押さえつけて無理やり治療をする。
- 本人に説明して理解してもらい、協力を得て一緒に治療をする。
この2つしかありません。
当院では、お子さまを無理に押さえつけて治療を行うことはありません。もしこのような治療が必要な場合は、専門の施設をご紹介させていただいています。
お子さまの理解・協力を得て治療を行うには、事前の準備が必要です。
まずは1人で診療用のイスに座っていただき、落ち着いて話を聞いていただける状況を作る必要があります。泣いている時は興奮状態になっていますので、話を聞いていただくのも困難です。何より治療自体も危険を伴います。そのため、お子さまが落ち着いていない状態で、治療を開始することはありません。
しっかりとした治療を行うためには、落ち着いた状態でイスに座っていただくことが必要ですので、慣れるまでには回数を重ねるしかありません。
もし虫歯ができて治療が必要な場合は、ご両親ではなくお子さまを中心にお話をさせていただきます。レントゲンの説明をしたり、治療に使う道具をひとつひとつ見せて実際に水を出したり、音を出したりして、本番と近い状態を体験していただいてから、実際の治療に臨んでいただく流れになります。
子どもの虫歯治療も麻酔をするの?
当院の虫歯治療では、よほど小さなものでない限り、必ず麻酔を行います。
これは、お子さまの場合も同じです。乳歯であっても、削れば痛いからです。子どもは素直ですから、痛いものは痛いと言って我慢してくれません。痛みを感じた瞬間から泣き出してしまいますので、そのまま治療ができなくなることもあり得ます。
ご両親から「別の病院では麻酔なしで治療した」というお話を伺うことがありますが、このような場合、かなりの確率で虫歯が残ってしまっています。
本来、虫歯治療では、虫歯をすべて取り除く必要があるのですが、麻酔をしないとなると、痛みを感じない範囲までの治療となり、すべての虫歯を取り除くことができません。
この状態では、内部にまだ虫歯が残っているため、詰め物がすぐに取れたり、残った虫歯が進行して強い痛みが生じるようになり、最終的には歯の神経を取るなどの大きな治療が必要になってしまいます。
虫歯治療で大切なのは、何よりも虫歯をきちんと取り除くことです。そのためには、できるだけ痛みを感じない状態を作ってから、しっかりと治療を行うことが必要です。

子どもは麻酔の痛みを我慢できるの?

全身麻酔ではないため、痛みをゼロにすることはできませんが、現在の麻酔は道具も進歩してきているので、麻酔をするよりも転ぶ方が痛いくらいです。
お子さまには、事前にこの事実を説明してから治療を行います。麻酔をすると伝えれば、お子さまも顔が引きつりますが、痛みは許容できる範囲であることを事前に知ってもらうことで、安心して治療に臨んでいただけます。
大人でも「痛くないですよ」と言われていたのに痛かったら不信感を抱くように、子どもも「嘘をつかれた」と思えば、次からは治療をさせてくれなくなります。
そうならないためにも、お子さまが相手だからといってごまかすようなことはせず、事前にきちんと説明をしてから麻酔を行い、治療を行うことが大切です。
ただし、このような事前のトレーニングや説明は、緊急性を要する大きな虫歯の治療の際には行うことができません。痛みが出ているとなれば、早急に治療を行う必要があり、トレーニングや説明を行う時間的余裕がないからです。
定期的に検診を受けていれば、虫歯がまだ小さいうちに治療が可能になるので、これらのトレーニングや説明を行うことができます。
歯医者や治療に徐々に慣れていくことで、歯医者に対して苦手意識を持つことなく、協力的な形で歯の健康を保てるようになるのです。
お子さまの歯の健康を守る当院の取り組みとは?
当院では、患者様の歯の健康をお守りするための取り組みとして、さまざまなサービスを行っています。
ご自宅でのケア方法をお伝えするのはもちろん、初診時・定期検診時には、ご自宅でお使いいただけるおすすめケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・フロスなど)のプレゼントも行っています。
歯の専門家が選ぶケア用品できちんとケアができれば、大切な歯をいつまでも健康に保つことが可能です。
また、虫歯予防を目的として、フッ素の塗布や、フッ素をイオン化させて歯に取り込みやすくするフッ素のイオン導入も無料で行っています。唾液中の細菌(虫歯菌・歯周病菌)の活動性を調べる唾液検査も無料で行っていますので、ご希望の際はお気兼ねなくお申し付けください。
なお、これらのサービスは、子どもの患者様だけでなく、大人の患者様にも無料で行っています。ぜひ、ご家族そろって健康な歯をキープしていただけたらと思います。

お子さまの歯並びが気になることはありませんか?


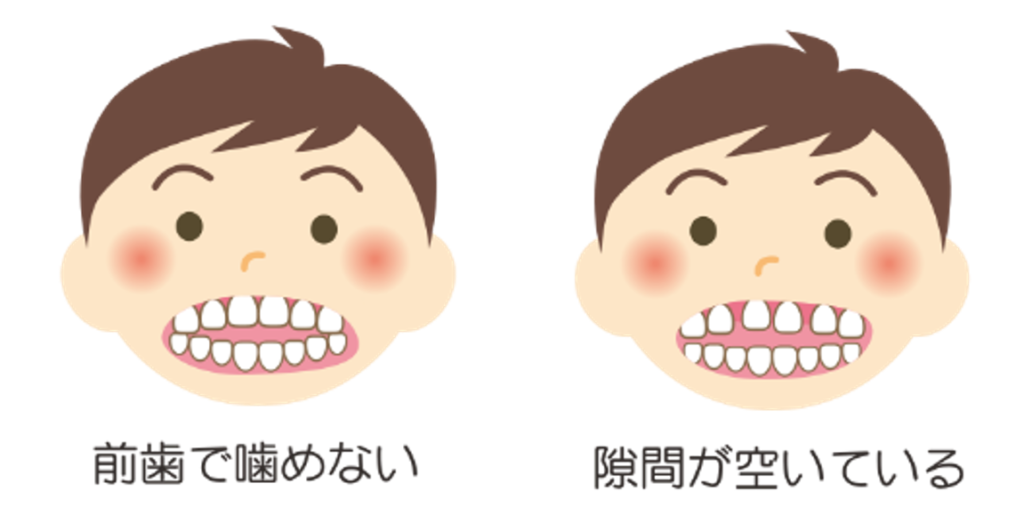
毎日の歯磨きや1歳半検診、3歳児検診、小学生になれば学校検診など、お子さまの歯並びについては、さまざまなタイミングで気になることがあると思います。 そのまま放置すると、下あごが長くなったり顔が横に歪んだり、見た目に影響が出るだけでなく、場合によっては咬み合わせ・顎の関節への負担・発音・滑舌・見た目・ケアのしやすさ・食べかすの溜まりやすさなどにも影響が出る可能性があります。
歯並びが変化しつつある成長期に治療を行えば、顎の成長する力を利用して比較的早く治療を済ませることができます。永久歯全体をレントゲンで確認しながらトータルで治療計画を立て、最適な治療開始のタイミングを見極めることが重要です。
当院では、お子さまから大人の方まで、症状に応じて治療が可能な矯正の専門医(認定医)が担当しています。
矯正治療に関する詳細については、こちらのページからご覧ください。
こどもの歯並びは噛むことから

院長 太田 智也
未就学児の親御さんから「子どもの歯並びが心配」というご相談をよく受けます。
実際に診てみると、多くの場合、乳歯がまだ完全に生え揃っていなかったり、乳歯は生えていても永久歯がまだ見えていなかったりする時期です。
歯並びの治療として歯列矯正がありますが、それは早くても小学生になって、6歳臼歯という大人の歯がある程度生えてから。そのため、当院ではそれまでの期間、矯正治療を行うことは基本的にありません。
では、幼少期にできること・・・それは、食事の際にしっかり噛むことです。
現代の子どもたちは柔らかい食べものを好む傾向があり、十分に噛まずに飲み込んでしまうため、顎の骨の発達に影響が出ていると考えられています。もちろん、昔と比べて子どもの顔が小さくなり、歯が生えるスペースが不足していることや、生え変わりに時間がかかることも原因のひとつかもしれません。
ただ、食べものをしっかり噛んで食べることで、歯から骨へ刺激が伝わり、骨の発育が促進されることがわかっており、特に、前歯でしっかり噛むと前歯部分の骨が、奥歯で噛むと奥歯部分の骨が発達することが証明されています。
実際、どういったものをどれだけしっかり噛んで食事をしていたかで、顔立ちは変わります。兄弟で顔が全く同じにならないのは、噛むことも関係しているんですね。
ちなみに、アフリカの原住民の方たちで、歯並びに問題のある人はかなり少ないようです。その理由は日本と食生活が異なり、固いものをしっかり噛んで食べているからだと言われています。
また、きちんと噛むことで、食べものを食隗と言われるペースト状にし、飲み込みやすくすることができます。噛むことで分泌される唾液には、殺菌作用や虫歯になりやすい酸性の状態から中性に戻す効果もあるので、噛むことはあらゆる意味において大切です。
将来、できるだけ矯正治療をせずに済むように、今のうちからお子さんの骨の発育を考え、よく噛んで食事をさせてあげましょう。
お子さまのお口が「ポカン」と開いていることはありませんか?

お口を「ポカン」と開いている状態は、「ポカン口(クチ)」と呼ばれます。
この「ポカン口」は口呼吸のサインのひとつと言われていますが、口呼吸は万病の元と言われているのをご存知でしょうか?
人間は鼻から呼吸をすることで、鼻毛がフィルターがわりになって、病気のウイルスや細菌などが肺にいかないようになっています。しかし、口呼吸の場合は、フィルターがないので、吸った空気がそのまま肺に運ばれてしまい、病気になりやすいと言われています。
歯科の領域では、口呼吸で口の中が乾燥しやすくなって口臭が強くなったり、唾液の分泌が減ることで殺菌作用が低下して、虫歯や歯周病になりやすくなったりと、さまざまな影響が出てきます。
では、なぜ口呼吸になってしまうのでしょうか?
実は、口呼吸のお子さまの特徴として多いのが、舌の位置や動きに問題があるということです。年齢的にアデノイド(扁桃腺)が大きかったり、アレルギーなどが原因で口呼吸になることもありますが、多くの場合は舌の運動機能に問題があります。
本来、何もしていないとき、舌は上アゴに張り付いているのが正しい状態です。しかし、舌の運動機能が低下している場合、舌が下の歯の内側に落ちています。この状態では、気道が圧迫されてしまうため、鼻呼吸よりも口呼吸が楽になり、結果として口呼吸になってしまうのです。すると「ポカン口」になりやすくなり、だんだんと顔立ち(骨格)や歯並びに影響が出てきます。
たとえば、舌を上アゴに張り付ける習慣がないと上アゴが刺激されないため、上アゴの成長・発育が鈍化して、歯並びや噛み合わせが悪くなります。一方で、下アゴの刺激が過剰になることで下アゴが過成長して、噛み合わせがより悪化します。
このように、歯並びや嚙み合わせは、舌の影響も強く受けているのです。
しかし、お子さま自身が舌の運動機能の低下を自覚して訴えてくることはありません。また、舌の動きは外側からはわからないため、保護者の方であっても、お子さまの舌が普段どのように使われているかを確認することは難しいと思います。
ここでサインになるのが「ポカン口」です。もしお子さまのお口がいつもポカンと開いているようであれば、口呼吸になっている可能性があります。
大事なことは、口呼吸をやめさせることではなく、口呼吸になっている原因に気付き、適切な形で鼻呼吸に変えていくことです。
当院では、歯のケアや治療だけでなく、お子さまのお口の機能を改善するMFT(口腔筋機能療法)という治療も行っています。
お子さまのお口に関して気になることがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連治療
子育て中のお母さんへ

お子さまとの通院やお子さまの歯やお口のケアについてご案内しています。
矯正歯科

歯並びや噛み合わせなどのお悩みを解決する矯正治療についてご案内しています。
MFT(口腔筋機能療法)

お子さまのお口の機能改善を行うMFT(口腔筋機能療法)についてご案内しています。